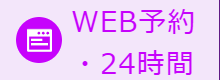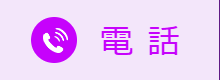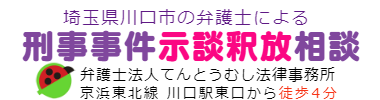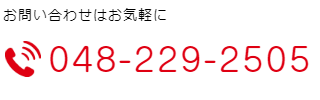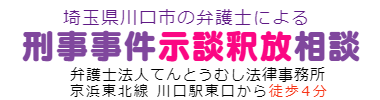起訴までに23日間も身柄を拘束される可能性があります。
この逮捕後から勾留、勾留延長で最長23日間に、警察や検察の捜査がされて身柄を解放するかや起訴するかどうかなどの判断が行われます。
弁護人は、この期間内に示談活動や意見書の提出などをして被疑者の不起訴処分や早期の身柄釈放を働き掛けることになります。
逮捕・勾留の流れは以下の通りです。
- 警察に逮捕された場合であっても軽微な犯罪などで直ぐに釈放される場合もありますが、勾留された場合には最長23日間は釈放されません。
- 警察署に48時間、検察への事件引継も含めると72時間つまり3日間は逮捕による身柄を拘束が続く可能性があります。検察官が勾留を請求するかどうかを判断し、裁判官による勾留質問が行われて勾留をするかどうか判断がなされますので、この2、3日の間に釈放を認めるべき資料を収集して、検察官や裁判官に釈放を働きかけることが重要です。
- 裁判所による勾留決定がされれば、10日間、その後、勾留の延長決定がされれば追加で10日間の合計20日の勾留がなされる可能性があります。
- 警察署内には留置場という施設があり、現場に同行するなど外出予定があるか取り調べ室に呼ばれるなどがなければ留置場内で過ごすことになります。
逮捕されて勾留される前の間は,弁護士以外は,逮捕された人に面会をしたり連絡を取ることはできません。
もちろん,逮捕された人も弁護士を呼んでもらうことは出来きるだけで,部外者に連絡を取ることは出来ません。したがって、この段階で逮捕された人の無実を証明する、または、被害者と示談するなどの身柄を解放のための活動をしてあげられるのは実際には弁護士以外にはいないと言えます。
逮捕された人は突然のことで気が動転している場合もあります。
また留置場では逃亡や自殺防止のため不自由な思いをします。
お風呂も数日に一度しか入れません。
移動も手錠腰縄をしてとなります。
弁護士が早く面会に行くことで無罪の証拠を収集する、まては被害者との示談の意向を確認して連絡を取るなどの身柄解放のための活動をすることで逮捕された人を励ますことが出来ます。
逮捕された場合には,弁護士を早くつけることが何よりも重要になります。
裁判官が逮捕に引き続いて勾留というさらに長い期間の身柄拘束を認めるとさらに10日間身柄拘束が続きます。
そしてその10日間に検察官が捜査を終了することが出来ないことに,やむを得ない理由があるときには勾留の延長として10日の身柄拘束が続きます。
起訴された場合。
検察官が起訴した場合は、そのまま勾留(起訴後勾留)として身柄拘束が続きますので釈放されないままです。
そのため、裁判所に証拠を隠滅しないことを約束し、事案ごとに個別に定められた保証金を納付する代わりに身柄拘束を解いてもらう手続(保釈請求)をする必要があります。